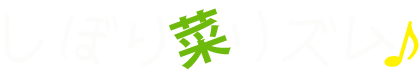父の戦争、母の戦争
終戦時父は、15歳、母は12歳。現在、87歳の父と85歳の母。
[ad#co-1]私の両親は、「第2次世界」を経験した世代の最後の世代なのではないでしょうか。
戦時中に生きたそれより下の方達は、小さくてあまり記憶にない方の方が多く父や母たちが戦争を知っている最後の年代だと言えるでしょう。
戦時中、父も母も10代で直接戦争に従事した訳ではありませんが、戦時下の空気というものを肌で感じた世代だと思います。
「今」を逃したら永久に父や母が体験した戦争の聞くことが出来なくなるかもしれない。二人が生きているうちにと思い、戦争当時の話を聞いてみました。
まずは、父の戦争体験談です。
父の戦争

戦争中、父は何をしていたか何を思っていたか聞きたくて父が入院している病院に行き、戦争当時の話をしてもらいました。
父の話を聞いていて特に「劇的」なことはありませんでした。
小学校6年(昭和16年)から父は、祖父の転勤で中国の北京に暮らしていました。北京在住の3年余りは食料も潤沢にあり、戦争の「色」もほとんどなく至って平穏に暮らしていたそうです。
中学3年(昭和20年)で天津の日本租界に引っ越して、そこで終戦なりました。
終戦の年まで日本人学校に通っていましたが唯一、戦争に関わったことは昭和20年、中学3年のときに「勤労動員」されたことです。
初めの頃の勤労奉仕は、学校の校庭の整備や修繕を行うために自宅から学校へ通っていたそうです。
しかし終戦が近くなると、同級生男子全員軍隊のトラックの荷台に乗せられて宿泊施設に入れられました。そこで家族から離れて寝泊りしながら、毎日、道路の整備や穴掘りをしたということです。
何故、中学生の子どもがシャベルやつるはしを持って土方仕事をしたかというと、働き盛りの若い男性が「徴兵」でいなくなり労働力不足を補うために行ったということです。
8月になると、工場で「爆弾」作りに動員されましたが、そこですぐに終戦になったそうです。
引き揚げ
終戦後、父の場合は比較的運がよく半年後の2月頃に日本に帰る引き揚げ船に乗ることが出来ました。
ただ、荷物はリュックなど手で持てるものだけしか持って帰ることが出来ず、家財道具はほとんど置いてきてきたそうです。
このとき父には、中国で生まれた1歳になる弟(私の叔父)がいて、その乳飲み子をよく連れて帰って来たと言っていました。
幼子を現地の人に託して帰る(後の中国残留孤児)満州開拓団のような壮絶な引き揚げとは違い、天津からの引き揚げは比較的平和的でした。
藤原ていの『流れる星は生きている』で着の身着のまま、飲まず食わず、命からがら満州から引き揚げてきた人達とは比べものになりません。
それでも、天津の港の体育館のような場所に3日ほど待機させられた後、客船ではなく戦車を乗せる貨物船に乗船させられたので雑魚寝のような状態で船の中で過ごしたということです。
教育ロス

父は、戦時中の食糧難のときには中国にいたので特に「ひもじい」思いはしていません。北京では、比較的物も豊富でいい生活をしていたようです。
空襲にも遭っておらず、家族を戦争で失うこともありませんでした。悲惨な体験こそしていませんが、戦争の影響が出たのが「学校教育」です。
終戦近くなると学校の機能が停止してまともに教育を受けられない教育の空白期間が、1年近くありました。終戦時は、学徒動員でほとんど授業を受けられませんでした。
終戦後も通っていた日本人学校が廃校になり、引き揚げまで家でプラプラしていたそうです。
小学校高学年で尋常小学校から「国民学校」になり、「修身」や「国史」(天皇を中心とした歴史)の授業や銃剣など戦争教育が色濃くなってきました。
父は、「教育勅語」や「軍人勅諭」など暗記させられ今でも半分くらい覚えています。
多感な時期に戦時下の教育で刷り込まれた頭で聞いた天皇の「玉音放送」(父は、中国で聞いたそうです)はどう感じたのでしょうか。
それまでは、「天皇は神様(現人神:あらひとかみ)」「早く大人になって、天皇陛下に忠誠を尽くしなさい」「いざという時は天皇陛下のために戦って、名誉の戦死を遂げなさい」
「神様である天皇が統治する日本は神の国、国民は神の子、日本の戦争はすべて天皇のための戦いで、悪いのはすべて外国」と何年も教わり続けたのです。
終戦と同時に学校で教わった価値観が180度変わってしまい、そのギャップをどう埋めたのか。今まで受けてきた「教育」はいったい何だっただろうと全否定されたような気持ちだったと思います。
しぼり菜リズム
父は、記憶力がいい方でこの頃のことをよく覚えていて、私が質問形式で当時のことを聞くと記憶の断片をすぐに拾い集めてくれました。
ただ、子どもの目で見たことしか知らないので、大人の事情や真実は分からないのです。
亡き祖母が話をしてくれたこともありましたが、そのときもっと真剣に聞いていればよかったと今さらながら思います。