見るべき映画は、たくさんありますが、多過ぎて紹介しきれないので、「白黒」「日本映画」に絞ってベスト3を選びました。
[ad#co-1]どれも今更、言うまでもない名作映画で、やっぱり時間を割いても見る価値はありますね。
それでは、第3位から
3位 7人の侍
1954年 黒澤明監督
エンタメ性とそれぞれキャラが立った7人が面白くて、3時間以上の長編だけど見飽きないです。
CGなどない時代、逆になかったからこそこんな迫力のあるシーンが撮れたのか
莫大な時間と費用を費やして撮影して、スタントマンを使っていたとしても危険なカットがあり命懸けで臨場感あるシーンを作り出すことができたのでしょう。
映画なのに皆、案外あっさり亡くなってしまうのだけど、現実もそんなもんだし、特に戦国時代はこんな風に人が沢山死んでいるはずです。
久蔵や菊千代といったメインキャラクターが命を落とす瞬間は、引きのカメラワークで撮影され、アップやスローモーション、抒情的な音楽を入れるより悲しみが後を引くから不思議
7人の侍がチームを結成する過程のストーリー性、一人ひとりのパーソナリティを掘り下げキャラクターが明確になるにつれそれぞれの人物に感情流入していまう中盤、クライマックスの戦闘シーンは迫力に満ち映画ならではの醍醐味が詰まっています。
稀代の名優達に混じって、野武士に家族を皆殺しにされた老婆には、実際に空襲で家族を亡くした一般女性が演じていてそのリアルな迫力に圧倒されます。
いい映画には、いい音楽がつきものだけど「7人の侍」も例外ではなく音楽だけで情景が浮かんでくるし、「菊千代のテーマ」のような音楽は、キャラクターの個性と結びつき人物の輪郭線を強める役割をします。
クセの強い侍達の中で、子どもの頃、素敵なおじ様だと思っていた木村功が、美青年で可愛いいなあとほっこりしました。
2位 雨月物語
1953年 溝口健二監督
若い頃、父がこの映画を家のテレビで観ていて京マチ子の「まろ眉」が気持ち悪かったが、ときに童女のようなあどけなさが見えたり熟女のような妖艶さも半端ないときもあり、般若のような恐ろしい顔と自在に演じ分け改めて映画を観て実に魅力的な俳優だと思いました。
逆に名前もないような庶民の妻を演じた 田中絹代の貧しいながらも真の幸せを追い求める慈愛に満ちた役が京マチ子と(いい意味で)対照的で印象に残ります。
男の野心と女の情念といった人間には、「欲」がありそれに捉われるとどうなるか二度と取り返しがつかないというのを寓話的に情緒的に描いていて
怪奇物語だけどこの人間の愚かさは、自分の中にも潜んでいてちょっとしたことで、顔を出してしまうのがこの映画の真の怖さです。
「雨月物語」という古典がベースとなったをオリジナルの物語で、朽木屋敷からの宮木の亡霊の場面は、現実と夢幻の世界の境界線を曖昧にしているところなど秀逸だと思いました。
霧が立ち込める湖を一艘の舟が都に進んでいく光景は、墨絵のようで白黒映画ならではの映像美が凝縮されています。
1位 東京物語
1953年 小津 安二郎監督
とにかく沁みます
「7人の侍」と違いエンタメ的要素がなくて日常を淡々と撮り続けたこの映画は、若い頃観ていたら面白くなかったかもしれません。
この年齢だからの1位です。
それは、老夫婦の老いていく気持ちが分かりと子ども達の親への悪意のない甘えの気持ちの両方が分かる年になったからです。
この映画では、娘の杉村春子だけ演技をしていて、小津監督は、抑えた演技を役者に要求しセリフは皆、棒読みなのです。
だから長女の杉村春子の悪意のない嫌らしさみたいなものが際立つし、原節子も少し演技をしていて?ヒロイン感が出ています。
子どもの立場から見ると長女は、長女なりに尽くしていて悪い人ではないいたって普通の人なのだけど親からみればその薄情さは寂しい限りで、紀子の「誰だって自分の生活が一番、大事になのよ」というセリフが物語の核心になっています。
とみが尾道から東京に着いたときは、「東京は、案外、近い」みたいなセリフがあったけど帰りは、「やっぱり、(東京は)遠い」と言っていてこの間接的な物言いは、子ども達との心の距離を表して切なくなります。
それにしても、原節子のときには神々しさを感じるオーラや内面から滲み出る輝きといい、私の父が原節子のファンであったのがよく分かります。
いつも思うのだけどオーラや品、色気、透明感って出そうと思っても出せるものではなく生まれ持ったものなのでしょう
とみにしても紀子にしても所作が美しく、紀子の美しい日本語とともにこういうものが、未来に受け継がれていないのは日本文化の損失かと思います。
(広島弁の周吉やとみもいい味出してます)
映像では、画像は、パーンやズームも使わない人間の目と同じ(標準)画角で撮っていて、とみが亡くなった朝の時間の経過を表す尾道の朝霧の港のインサートカットなども効果的で、ロングショットの土手の上で遊ぶとみと孫の勇の映像はまるで1枚の絵画を見るようです。
カメラを固定して同じ画角で何度も同じ場所で撮っているのだけど、周吉ととみの住む尾道の家の窓がいつも開け放たれていて、ご近所のおばさんが通るといつも挨拶代わりに短い会話を交わし
最初の場面は、部屋の中で東京への旅支度をしている夫婦に窓から「子ども達も立派になってさぞかし楽しみでしょ」と声を掛けます。
ちょっと話はそれますが、終始温和で優しい周吉だけどこの旅支度のシーンでは、町医者である息子の妻に対して終始命令口調まではいかないものの周吉の鞄に空気枕を入れた入れないのやり取りで明治気質の一面が出たりして、とみもそれを普通に受け入れるところなど時代が表れています。
(サッシでピシャリと閉めた窓と違い、家の中の様子も丸見えなのもいい)
同じ場面の2回目は、夫婦二人だったのがとみが亡くなり周吉一人になった部屋の様子を同じご近所のおばさんが見て「寂しいでしょう」と声を掛ける
周吉が「気が効かんやつじゃったが、おらんと寂しいなあ」と返し、あ~もうとみが居ないんだってリアルな現実を突きつけられ胸が締め付けられます。
さもない日常の中の無常を家族を通して描き出しているのだけど、終盤は再生に向けての出発を暗示させる場面もあり、紀子の変わらぬ優しさや末娘の存在とともに虚しさだけでは終わらないのが物語の救いです。
映画の蒸し暑い夏の日の家族の営みが蘇り、私にとってモノクロームの新たな記憶を作った映画なりました。
この映画が国境や時代を超え人々の記憶に焼きつくのは、「人間の生と死」とか「家族とは」という人類共通のテーマを扱っているからでしょう
陽だまりのような笠智衆、昔から好きだけどやっぱりいいなあ~
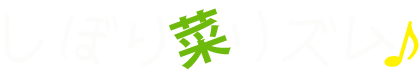

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1da5f8c8.384ae07f.1da5f8c9.6f9ae89d/?me_id=1229477&item_id=10514053&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjoshin-cddvd%2Fcabinet%2F800%2Ftdv-25080d.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15a8b7ba.957f61e3.15a8b7bb.83af7322/?me_id=1213310&item_id=18339475&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1407%2F4988111151407.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15a8b7ba.957f61e3.15a8b7bb.83af7322/?me_id=1213310&item_id=16399745&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6618%2F4988105066618.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)














