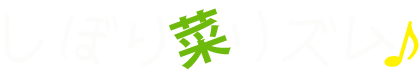(「露に濡れたハリエニシダ」ジョン・エヴェレット・ミレイ 1889~1990年)をバックに『テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ』(国立新美術館))
[ad#co-1]『テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ』(国立新美術館)と『虫めづる日本の人々』(サントリー美術館)に行った感想です。
テート美術館
『テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ』(国立新美術館)へ行きました。
ロンドンのテート美術館のコレクションの中から「光」をテーマとした作品で120点を展示した美術展です。
18世紀末から現代まで約200年の間「光」が意味することや作品における役割や「光」の表現が、時代によってどう変わっていったかといのが分かるように展示されています。
季節や時間とともに変わりゆく光と色彩の変化を生涯にわたって追求した「光」の画家クロードモネ

「エプト川のポプラ並木」クロードクロード・モネ 1891年
モネは、このポプラ並木や水連など同じ題材ののものを繰り返し描き、様々な時間帯、季節、天候のもとで光が醸し出す空気感を捉えながら表現しました。
このように光そのものや光の反射の表現を変えることで、そのときの風景の一瞬の時間を絵の中に閉じ込めようとしたのです。
モネに影響を与えたのがイギリスの国民的画家ウィリアム・ターナーです。
ターナーも「光の画家」と言われ空と水と光の表現を追求し、自由で幻想的な風景画を描いてきました。

「湖に沈む夕日」ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー 1840頃
ターナーの作品が多数展示されいますが、こういうピンボケのような絵が多く近寄ったり離れて見るも何が描かれているかよく分かりません。
しかし、ターナーは、光の反射や屈折、光と影の関係について学生に講義していたり、「反射して部屋の内部の様子が映りこんだ球体の図」など展示されていたものを見ると理論的に光を追求していたことが分かります。
それを知れば、光に対して様々なアプローチをして表現しようとしていたことが伺え、だからこういう描き方もあるかと思いました。
抽象的なターナーと比べて、「光」の表現が分かりやすく表現されていたのがこの絵

「ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡」ジョン・ブレット 1871年
撮影禁止だったのか、私は写真に撮っていなくてポスターの写真だけど実際にはかなり大きな絵で、きっとこういう絵を好む人は多いだろうと思いました。
「天使のはしご」と呼ばれる放射線状に降り注ぐ陽光をそのまま表現し、美しい空と海と光による光景はまるで楽園のようです。
こういう全体が光に満ちた作品ばかりでなく、光が差し込む室内を描いた絵のように光と影のコントラストで「光」を表現しているものもあります。
自然現象のよる光の他「人工的」な光で表現したものが後半の現代アートの作品です。
インスタレーションや視覚体験や体験型の展示は、大人のテーマパークのようでした。
その一つが、印象派の絵画が並ぶ展示室の中央に鏡で出来た立方体のオブジェ

「去ってゆく冬」草間彌生 2005年
立方体の無数の開けれた穴から中を覗くと、草間彌生の作品だからか、水玉模様のような丸い窓が延々と続き無限で複雑な光景が繰り広げられています。
立方体の全ての面が鏡になっているので周囲の色や形、作品や観客などを映し込み内部に設置された複数の鏡の反射によって万華鏡のような複雑な光景になるのです。
こういう光の反射を用いる作品もあり「光」は、実態のあるものではないだけに様々な表現が可能になるのかと思いました。
このように多様な表現が可能な光だから、多くの芸術家が、光をどう表現しようか取り組んできたのでしょう。
■テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ
- 会場:国立新美術館
- 会期:7月12日(木)~10月2日(月)
虫愛ずる日本の人々

サントリー美術館に来るとほっとするのですね。
美術館自体もさほど大きくないので、作品の数も多過ぎずビックイベントでない限り平日ならさほど混んでおらずじっくりと鑑賞することが出来ます。
ミッドタウンという複合商業施設にありながら、隈研吾が設計し木材を使った和の雰囲気も落ち着きます。
そんなサントリー美術館で開催されているのは、『虫めづる日本の人々』です。
入り口からもう鈴虫の音が流れ、雰囲気を盛り上げ
蛍の点滅したような空間、蝶の陰の演出とサントリー美術館は、音の効果や空間を上手く使うなあと思いました。
日本美術は、草木花鳥がモチーフとして多いけど、「虫」もまた重要なモチーフで美術作品ばかりではなく物語や和歌などにも登場します。
特に人気のある蛍や鈴虫などの鳴く虫は、『源氏物語』『伊勢物語』など登場人物の心情を代弁するものとして登場しています。
そういえば、光源氏が、秋の夕暮れ、庭に鈴虫を放ち女性を口説いたり、女性の部屋に隠れて蛍を放つといった虫を小道具として演出する場面があったか
平安時代、貴族だけのものだった虫の音を聴いたり蛍を愛でる「虫めづる文化」は、江戸時代になると風雅な娯楽や年中行事として庶民にも広まり作品にも表現されるようになりました。
喜多川歌麿の「夏姿美人図」(1794~95年頃)は、直接、虫は描かれていませんが女性が鏡を持ち化粧をしている足元の団扇の上に蛍籠が置かれ、蛍狩りに出掛けることが分かります。
蛍狩りデートでしょうか
文学的に蛍は恋情と関連が深く、歌麿は女性の淡い恋心を表現したのかもしれません。
上村松園の美人画「むしの音」も同じように虫の音に耳を澄ます女性の絵で、虫そのものは登場しません。
同じ歌麿の植物や虫の描画力が素晴らしい「画本虫撰(がほんむしえらび)」(1788年)は、狂歌絵本となっていますが植物と虫の図鑑といってもいいくらいです。
美人画のイメージが強い歌麿ですが、花鳥画においてもその才能が発揮されていたのは新鮮でした。
中国からもたらされ多くの絵師達にも影響を与えた「草虫図」の枠組みを超えたこのような虫の特徴を的確にとらえた精微な図譜的なものも江戸時代以降盛んに描かれ
歌麿の他に伊藤若冲、酒井抱一、葛飾北斎などの絵師達も描いていて単に花や植物だけの絵よりどこにどんな虫がいるのだろうと探す楽しみもあって私は、好きかもしれません。
今回、伊藤若冲の「菜蠢図」は、場面替で見れませんでしたが、以前、細見コレクションで見た「糸瓜群虫図」 の精密な描写はよかったです。
「きりぎりす絵巻 上巻」(住吉如慶)は、虫が姫をめぐって恋愛劇を繰り広げるという擬人化された虫達のの恋愛模様を描いた絵巻で、下巻も見たかったです。
蟻がお米を一粒残さずせっせと運んで難題を解決する「天稚彦物語絵巻 下巻」もストーリー性があって面白いです。
蚊やゴキブリやハエは嫌だけど東京にも身近に虫はいて「虫愛ずる精神」を日本の独自の文化と大切にしていけたらと思いました。
■虫めづる日本の人々
- 会場:サントリー美術館
- 会期:2023年7月22日(土)~9月18日(月)
しぼり菜リズム(まとめ)
『テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ』(国立新美術館)
この展覧会は、ロンドンのテート美術館のコレクションから選ばれた「光」をテーマとした作品約120点を展示しています。
18世紀末から現代までの約200年間にわたって、「光」の意味や作品内での役割、光の表現方法が時代とともにどのように変化してきたかが展示されています。
モネは季節や時間とともに変わる光と色彩の変化を追求し、ポプラ並木や水連などの同じ題材を描き光の表現に取り組みました。
空と水と光を幻想的に描く風景画家ウィリアム・ターナーは「光の画家」と称され、ピンボケのように見える作品も実際には光の反射や屈折を理論的に探求し、光の多様な側面を表現しています。
展示はさらに多様なアーティストによる作品を通じて、自然現象の光の他に人工的な光の表現も探求されていました。
「光」は実体のないものであり、それをどのように捉え表現するかは芸術家の創造であり、展覧会はその多様性と魅力を多く紹介したものでした。
『虫めづる日本の人々』(ントリー美術館)は日本の美術作品における「虫」をテーマにしたものです。
日本美術においては、草木花鳥が重要なモチーフとして知られていますが、「虫」もまた重要な要素で蛍や鈴虫などの虫は、『源氏物語』や『伊勢物語』などの文学作品において登場し、登場人物の心情を象徴する要素として使われてきました。
平安時代には貴族の間で楽しまれていた「虫めづる文化」も、江戸時代に入ると庶民の間にも広がり、風雅な娯楽や年中行事として虫を愛でる習慣が広まりました。
また、中国からの影響も受けつつ、江戸時代以降には「草虫図」などの虫を描いた図譜的な作品も盛んに制作され、喜多川歌麿、伊藤若冲、酒井抱一、葛飾北斎など多くの絵師が制作しました。
「きりぎりす絵巻 上巻」や「天稚彦物語絵巻 下巻」など、虫が擬人化されて恋愛模様やストーリーが描かれた作品も展示されており、日本の独自の「虫愛ずる精神」が表現されています。