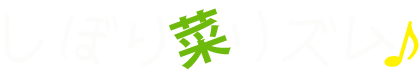世紀末、ウィーンで活躍した画家エゴン・シーレ(1890~1918年)が、昔から気になっていました。
[ad#co-1]20代の頃、どこで見たのか何の絵か覚えていないけど、少し不気味な絵が妙に印象に残り、シーレって決して嫌いな画家ではないと思っていました。
それから、シーレのことは忘れていましたが、再び『クリムト展』(2019年)で数点のシーレの絵に出会い、いつか、エゴン・シーレをきちんと見たいと思っていました。
作品に込められた思いは、想像以上に深い。官能的な女性を描いた【クリムト】の展覧会
でも、クリムトほど人気がある訳ではないので、シーレが主役の展覧会はないのだろうと諦めていたところ東京都美術館で30年ぶりにシーレの展覧会をやることが分かり、昨年から楽しみにしていました。
その展覧会が、『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』(東京都美術館)で、早速、初日明けに見に行きました。
今回は、レオポルド美術館の所蔵作品を中心に、エゴン・シーレの作品が50点、クリムトなど世紀末のウィーンで活躍した作家たちの作品と合わせて約120点が来日しています。
エゴン・シーレ
エゴン・シーレが夭逝の画家というのは知っていましたが、作風からてっきり精神を病んでゴッホのような亡くなり方をしたのかと思っていました。
(もしくは、無頼派のような生き方をした末に亡くなったのかと。)
でも、28歳で、当時、流行していたスペイン風邪で亡くなり、突如として身に降りかかった災難で自分の意思とは関係なく命が尽きたことを知りました。
そして、新型コロナが蔓延している今と似ている状況下も想像しました。
画家としての評価を得て、これから名声を得るであろう画家人生が強制終了してしまったシーレの人生ってどうだったのか。
画家として類い稀な才能を持っていたことやクリムトとの出会いという運のよさもあり、18歳で個展を開いたり早くに出世街道を歩き始めたのだけど私生活は、問題のある人だったようです。
モデルとなることもあった実の妹との近親相姦的な関係や少女達をアトリエに連れ込んで危ない絵を描いて少女誘拐の罪に問われたこともありました。
元クリムトの恋人のモデル、ヴァリーと付き合うも近所の裕福な家柄のアデーレとエーディトという姉妹に恋をして、恋人ヴァリーを捨て、妹のエーディトと結婚します。
結婚後もヴァリーとの関係は続き、エーディトの姉とも関係を持ち、二股三股、三角関係ならぬ四角関係のもつれた恋愛関係の中で創作活動をします。
シーレの私生活は、このように一見、破天荒に見えますが、画業のためにはいい意味でも悪い意味でも彼なりの努力をしていて、これもシーレ自身かと思いました。
美術のエリート校に入学するも自主退学してしまったのは、あえてレールから外れることで独自性を築いていこうという意思があったからではないか。
身分の低いヴァリーを選ばず、堅実な中産階級の娘と結婚したのも画家としての確固とした地位を築きたいという打算もあったから。
実際に援助も受けていたス―パスターのクリムトに近づいたのも下心があったから?
こういう書き方をすると、結構、売れるためにはしたたかだったのかって思われますが、どんなに才能があってもその才能だけではシーレの早熟な才能を開花させることが出来なかったでしょう。
世に認知されるのは、単に絵が上手いだけではなく自分をPRしたり、誰彼を利用するような処世術が必要で、それはどの時代でも同じなのです。
でも、一つ上を行くのであれば「絵画で何を表現出来るのか、常に新しいものを創作する」というテーマを追求することは必須で、シーレの頭に中は常にそのことが占めていたのだと思います。
だから、死や性のタブー視されていた部分も作品に積極的に取り込みました。
性描写など倫理的に問題視されるようなテーマを強調する作品を過激だと受け取られながらもシーレは、怯まず挑戦していきます。
この反社会的にも思える創作活動は、狙ってやった訳ではないが、結果、センセーショナルな画家として一世を風靡し、シーレの強烈な独自性は、新しい時代の可能性を切り開いていったのです。
シーレの絵に魅せられるのは

「吹き荒れる嵐の中の秋の木(冬の木)」1912年
私がシーレの絵が気になり魅せられるのはどうしてか、今までよく分かりませんでした。
でも、今回、作品を見て私は、シーレの色の使い方が独特で好きなのだと改めて思いました。
他の絵では見られないシーレらしい色があります。
例えば、今回のハイライトである「ほおずきの実のある自画像」(1912)は、シーレ自身を描いたもので、「母と子」(1912)などシーレの描く人の顔は青白く、血管のように赤や青の絵具を使い本来人の顔や肌に使わない色を使っています。
この使い方を間違えると不気味で幽霊のようになりますが、彩度の高い色を使いながら全体的にバランスが取れ違和感がありません。
また、ほおずきのオレンジや母子の真っ赤な唇の赤やオレンジの対比色の使い方が見事で、それが差し色になっています。
(同じようにモノクロの色調に赤、青、黄色の鮮やかな色を落とす写真家のソールライターの作品も好みです。)
ニューヨークが生んだ伝説の写真家『永遠のソール・ライター展』に魅了されて

「ほおずきの実のある自画像」のポスターの前で
ほおずきをバックしたシーレの顔色は悪く不穏で不健全なのだけど、オレンジの鮮やかな色が希望となり救いになっています。
こんな色の使い方で、シーレは、死や不安など常人には見えない感情を表現しているのでしょう。
暗い色調の中の赤、青、緑の強烈なオリジナリティが私にはお洒落でモダンにも見え、過去に見た絵やクリムトの展覧会での絵に後ろ髪を引かれたのもこのような唯一無二な色使いが、私の感性に合っていたからだと思いました。
ナルシスト?

絵画を再構成平面的にパッチワークのような風景画 ・「モルダウ河畔のクルマウ(小さな街IV)」1914年
エゴンシーレは、多くの自画像を描くとともに写真もたくさん残しています。

絵本『小さなお家』のような絵・「ランゲン・アム・アールベルク近くの風景」1913年
写真を見るとジェームス・ディーンのようなアウトサイダーっぽい哀愁がある美青年なので、自分をモデルにしているのも納得出来ます。

でも、明らかに自己愛に溢れたナルシストかと思われるような写真もあります。
彼は、自分の姿をひたすら観察し続け、100点以上も分身を生み出したのは、ナルシストであると同時に「自己肯定」のために自らを描いたのかもしれません。
経歴を見ると15歳のときに最大の理解者であった父を梅毒で失くしていて、その喪失感を埋めるように孤独や不安を炙り出すように描いていて、それが自己肯定に結びついているように見えるのです。
彼の枯れ木のような肉体とねじれた手足やヌードも耽美的なのは、自己肯定感を上げるための強烈な自己表現なのかもしれません。
最後にウィーンのレオポルド美術館の所蔵作品を中心に、シーレの油彩画やドローイングなど50点が来日しましたが、シーレの作品は220点あるそうで、欲を言えば、シーレの作品をもっと見たかったです。
そして、絵画で何を表現出来るのか、常に新しいものを創作し続けたシーレが、志半ばの28歳で亡くなっていなければどんな進化を続けたのか知りたかったです。
しぼり菜リズム(まとめ)

ミュージアムショップ
画家エゴン・シーレ(1890~1918年)の展覧会、『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』(東京都美術館)に行きました。
今回、レオポルド美術館の所蔵作品を中心に、エゴン・シーレの作品が50点、クリムトなど世紀末のウィーンで活躍した作家たちの作品と合わせて約120点が来日しています。
シーレは、画家としての評価を得て、これから名声を得るであろう28歳で、当時、流行していたスペイン風邪で亡くなりました。
画家として類い稀な才能を持っていましたが、実の妹との近親相姦的な関係や少女達をアトリエに連れ込んで描き少女誘拐の罪に問われたり、結婚後も元恋人や妻の姉とも関係を持つという奔走な私生活を送っていました。
シーレは、美術のエリート校を自主退学するも画家としては、死や性のタブー視されていた部分も作品に積極的に取り込み「絵画で何を表現出来るのか、常に新しいものを創作する」というテーマを追求し早熟な才能を開花させます。
売れるためにはしたたかだった部分もあるようですが、反社会的にも思える創作活動は、結果、センセーショナルな画家として一世を風靡し、シーレの強烈な独自性は、新しい時代の可能性を切り開いていきました。
以前からシーレに作品に惹かれたのは、暗い色調の中の赤、青、緑の唯一無二な色使いや希望にも見える差し色の鮮やかな色が私の感性に合っていたからでした。
シーレは、自画像や写真を多く残したのは、ナルシストであると同時に「自己肯定」のために自らを描いたのだと思いました。
最大の理解者であった父を15歳で失くし、その喪失感を埋めるように孤独や不安を炙り出すように描いていています。
彼の枯れ木のような肉体とねじれた手足やヌードも耽美的なのは、自己肯定感を上げるための強烈な自己表現なのかもしれません。
■エゴン・シーレ展
- 場所:東京都美術館
- 会期:2023年1月26日(木)~4月9日(日)