小説「レ・ミゼラブル」
ビクトリアユーゴー小説『レ・ミゼラブル』を買って、やっと読み終わりました。
[ad#co-1]緊急事態宣言が出てから、時間が出来たので長篇小説に挑戦しようと読み始めましたがなかなか進まずしばらく放置していました。
映画とドラマ版の『レ・ミゼラブル』を観てジャン・バルジャンが改心のきっかけを作ったミリエル司教やジャヴェルのことをもう少し知りたかったのと映画やドラマでは描かれていない詳細なストーリーを知りたかったから小説を購入しました。
アマゾンプライムビデオ「Theミュージカル映画」傑作2選その2『レ・ミゼラブル』
今回、購入したのが翻訳が豊島与志雄の岩波文庫版です。
この本で苦労したのが、豊島与志雄の訳が、1917年(大正6年)で、その時代の古い表現で読みにくいことです。(1987年に一部改訳)
そして、吾人、宸翰(しんかん)、爪繰(つまぐ)、別墅(べっしょ)、陋屋(ろうおく)、溝渠(みぞ)、蝋着(ろうちゃく)、鰥夫(やもめ)など日常であまり使わない言葉や古今東西古典からの引用も多く前後の意味がつながらなかったりして分かりにくい。
それと苦行を強いられるのが、物語の本筋から何度も逸れるユーゴーの視点で人生哲学、歴史、政治、思想、宗教観が延々と書かれていることです。
(当時、小説は単なる娯楽ではなく、歴史や社会を知るための道具という役割もあったようで、それでユーゴーは、本書のかなりのページを割いたのかもしれません。)
これは、当時の世情、パリの地理、宗教、風習、暮らしなど貴重な歴史的「資料」として読めば面白いのでしょうが、私にとってどうにも退屈でこの部分になると先に進まなくなってしまいます。
特にジャン・ヴァルジャンに盗んだ銀の燭台をあげて改心するきっかけを作った「ミリエル司教」とナポレオン軍が敗北した「ワーテルロー」の描写が長い長い。
でも、読み進めたかったので、長いユーゴーのうんちくともいえる余談を半分くらい斜め読みして「ワーテルロー」の章がやっと終わる最後に思わぬ「プレゼント」がありました。
それは、物語の後半への重要な伏線を張るテナルディエとポンメルシーが出会う場面で、ここで初めて膨大で退屈なユーゴーのうんちくに付き合ったかいがあったと思いました。
そして、「本筋」に話が戻ったときには、決して読みやすい文章ではないけれど「あれっ、読みやすくて面白いなあ」とユーゴーマジック、物語が生き生きと輝いているように感じました。
また、退屈と思われた小説で描かれる歴史的背景を押さえれば、登場人物の行動の必然性や思考などがその時代のリアリティーとして説得力を持って読むことが出来ると思いました。
ドラマや映画では、分からなかったこと
どうして、ミリエル司教と出会ってから変わったのか

映画やドラマを観て、一番知りたっかことはジャン・バルジャンが「ミリエル司教」の施しを得て、その後、人が変わり「聖人君子」のように善行を施していったかということです。
映画やドラマではこの分部が詳しく描かれていなかったので、「人は、急に改心して善人になれるものなのか」と気になっていました。
小説では、ミリエル司教の来歴や人となりや生活ぶりを長々と書き連ねていますが、ジャン・ヴァルジャンにとって、ミリエル司教は、「良き人(正しき人)」として愛を実践し、ジャン・ヴァルジャンに「無償の愛」を身をもって教えた一人の固有の人間だけでなく「神」のような存在だったことが分かりました。
(興味深かったのは、社交界 と色 恋 沙汰 に 明け暮れる 日々を過ごした後イタ リ ア へ 亡 命、一 家 の 没 落というミリエル司教の過去で、ミリエル司教でさえも最初から聖職者ではなかったことです。)
当初、ジャン・バルジャンは、ミリエル司教に温かい食べ物や寝床を提供されただけではなく、司教を裏切って盗んでしまった銀の燭台までを罪を問うことなく与えてくれた司教の行為を理解出来ずにいました。
罪人としてあまりにも長い年月を「憎悪」の中で生きてきたので、ミリエル司教の親切や慈愛が最初は、分からなかったのです。
むしろ、そのことに衝撃を受け悩みながらも社会に対する憎悪の延長で、ジャン・バルジャンは、少年の銀貨を盗んでしまうという罪を犯します。
このとき初めて、改めて、自らの行為を恥じて後悔をしミリエル司教が、ジャン・ヴァルジャンの裏切りを赦し、その上、銀の燭台までも分け与えてくれた行為や意味を真に理解することが出来たのです。
社会の不公平のために社会を憎悪していたジャン・ヴァルジャンをこの世ではじめて「人」として受け入れてくれ、人間の心で接してくれたミリエル司教の教えを実感したのです。
ジャン・ヴァルジャンは、ミリエル司教と出会ってすぐに生まれ変わり善人となった訳ではなくて、「正しき道」を進む覚悟をして生きていくまでは相応の葛藤があったという映画やドラマでは分からなかったジャン・ヴァルジャンの心境の変化を知ることが出来ました。
ジャヴェルの死の謎

ドラマや映画で、分からなくて知りたっかもうひとつは、ジャヴェルが「自死」をした理由です。
ドラマや映画、特に映画ではちょっと唐突な感じが否めなかったので、ジャヴェルの「死」が消化不良でした。
警官としてのジャヴェルは、「法(律)」こそが「正義」で絶対的な存在であり、法に服従することを信念に生きてきました。
ジャヴェルにとって、盗みを働き、何度も脱獄したジャン・バルジャンは、「法」の下では、極悪非道「悪」の権化だったと思います。
そんな犯罪者のジャン・バルジャンが、火事や船の事故で人を助けたり、馬車の下敷きになった老人を助け、コゼットの母であるフォンテーヌを助け、瀕死のマリウスを助けます。
ジャヴェルは、ジャン・バルジャンの市長としての「善行」も見て人々が幸せになっていくのも見てきました。
そこへきて、ジャン・バルジャンにとって忌むべき敵であるジャヴェル自身の命を救うことになり、ジャヴェルは、「法の正義」の上に「人間の正義」というものがあるのだといことを知ります。
この最も憎むべき犯罪者の善行で人が幸せになっていく姿を見ることは、「法の番人として、悪を追及すること」が自らの「アイデンティティ」のジャヴェルにとって、信じていたものが崩れていく瞬間でした。
法の下の悪をいくら追求しても人は幸せになれないこということをジャン・バルジャンによって知り、法の正義に忠実に従って生きてきた彼の基盤が覆されたのです。
だからって、現代の私達からすると何も死ぬことはないのではないかと思いますよね。
ましてや、キリスト教では、自殺は最も行ってはならないことです。
やはり、ジャヴェルは、「人間の正義」つまり慈悲や愛こそが人を幸せにすることを知った自分を許すこと出来なかったのでしょう。
ジャヴェルの誤魔化しの効かない不器用な真面目さでは、精神的支柱なくては生きていけなかったのです。
ともに今まで、自分をがんじがらめに縛っていた「法」から解放されたかったのかとも思いました。
まあ、ジャヴェルにとってジャン・バルジャンは、個人を超えた何か「象徴」のような存在だったのではないかと思います。
実は、小説では、ジャヴェルの心の襞や声を詳しく描いている訳ではなく、割と淡々とセーヌ川に身を投げて死んでしまいます。
だから、ジャヴェルの「死の謎」は、小説に答えがあった訳ではなく単に私が感じたことを書いているだけです。
そして、話はそれますが、小説では、ジャヴェルの死の間際、囚人への「待遇の改善」などを記した意見書を残したという場面があり、これは、ジャン・バルジャンの1片パンを盗んだという「罪」に対して、はるかに重い5年(脱獄を繰り返し19年に刑期が伸びた)の服役という「罰」に対する当時の(小説で描かれているような)社会のシステムへのユーゴーなりの反発みたいなものを落とし込んでいるのだなあと思いました。
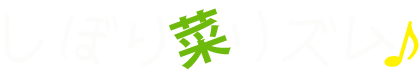

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e67b2f7.51e6d8ab.1e67b2f8.765002ee/?me_id=1275488&item_id=11440973&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookoffonline%2Fcabinet%2F2138%2F0016348967l.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)















