緩和ケア医が、がんになって
以前、「がんになって医者として誰よりも患者や家族に寄り添えると思っていたが自分ががんになって初めて、患者のリアルな苦しみに気づた」という緩和ケアの医者による投書が『朝日新聞』にあり目を引きました。
[ad#co-1]最近では、同じ緩和ケア医によるキャンサーペアレンツの西口洋平氏の訃報に際しての投書を『朝日新聞』でお見かけ掛けしました。
そのがんになった緩和ケア医というのが、大橋洋平氏で自身の闘病のことを書いた本が出版していると知り購入して読んでみました。
本のタイトルは、『緩和ケア医が、がんになって』(大橋洋平著・双葉社)です。
大橋洋平先生は、10万人に1人という希少ガンであるジストに罹患し、発症から手術、抗がん剤治療、転移までの闘病生活と抗がん剤治療を続けながら、医療現場に立ち続けていることなどをこの本に書いています。
医者目線と患者目線の違い
私が一番興味があったのが、今までがん患者を診ていた医者ががん患者になって何を感じたかということです。
(「医師」と「医者」の違いについて医師は、資格的なものを表し、医者は人間的なものを表す。医者は、医師よりも僅かだけど患者に近づいた立場に感じるということで自身については、本書で医者と書いています。)
大橋先生は、医者として診ていたがん患者というものと自身ががん患者の当事者になって見える景色が全く違うのだと書いていて、やはり医者として見るがんと自分がなるがんとでは全く違うのだと思いました。
ホスピス緩和ケアでは「がんになってもよりよく生きる」という言葉を使うが、患者になってみれば「よく」など生きられない。
病が重いほど患者のとっては、医者の力は大きい。
薬の飲み忘れなど我が身に降りかかってみなければ本当に分からない。
食べられなくても生きられる事実を書いた教科書はない。
消化液逆流も妻の提案の「飲み流し」で喉やけ、胸やけが減った。
このことは、教科書にはないことで、医学書に載っていることが全てではない。
と書いているように医者であり患者である大橋先生は、「医者目線」と「患者目線」の両方の目線で見ることやギャップを体験することが出来、患者になって初めて気づいたことも多くあったようです。
この医者じゃないと書けない患者側に立った視点が、鋭くてとてもリアルに感じました。
それは、以前読んだ本の『余命半年、僕はこうして乗り越えた-がんの外科医が一晩でがん患者になってからしたこと-』での西村元一医師も同様のことを書かれていました。
【がんになった医師の選択】医師と患者、両方を経験して、実現した。金沢マギー
大橋先生は、今まで、ホスピスの緩和ケア医として、誰よりも末期がん患者に向き合ってきたと自負しているように、がん患者(特に末期がん患者)の気持ちに一番近い場所にいた医療関係者であった思います。
それでも、実際には医者として接するがんと、患者として経験するがんは、全く別のもので、自分がなって初めて「患者のリアルな苦しみ」に気づき「言葉では理解しているつもりが甘かった」ということなのです。
患者風吹かせてしぶとく生きる

大橋先生は、がん患者でも決して模範的ながん患者ではありません。
手術に際して必要な抜歯を怖がって先延ばし、栄養剤をこっそり捨て、点滴は、早く流すように操作してしまうというなかなかやんちゃながん患者である。
過酷な治療や生命の不安に怯えてじたばたすることもあり医者でありながら弱音も吐き、我儘を言って周りに迷惑を掛ける。
がんから復帰して前向きなメッセージを発信している人はいるけれど、自分にはとてもあんなふうには言えない。
終末期において心身共に弱ってくると、「よりよく、自分らしくなんて、そうそう生きられない」と開き直るような患者なのです。
でも、そこからなのですね。大橋先生は
結局、がん患者は体の痛み、心の痛みに魂の痛みを抱えて苦しんで確実に弱っていることが多いのです。
にもかかわらず、緩和ケア病棟の患者は、我慢をしていることが多く、それをずっと診てきた先生は、こんなに苦しいのならそれを我慢していい人にならなくてもいい、苦しいのならば、叫べばいいと自分でも達観するようになります。
これは、大橋流に言うと「患者風」を吹かせるということで、「がん患者は、もっと患者風を吹かせて自分中心に好きなように生きていいのだよ」とがん患者や自身へのメッセージであり、これが「しぶとく生きていく」ことに繋がっていきます。
この「しぶとく生きる」ことは、末期のがん患者として、元気だった頃のような生活は諦めるけれど、現状で達成可能な目標のみを設定して、今、出来ることを頑張ればいいというものです。
限られる中で、せめてやりたいことを我慢せず「弱い患者である私」のままでよいから患者風吹かせながら今をしぶとく生きようとする前向きな生き方なのです。
足し算式の人生
大橋先生が、前向きに生きていくのに考えたのが「足し算命」というものです。
転移がんが見つかってからは、今日、明日、あさってと引き算してカウントダウンする「余命」を意識するのを止めて、今日から過ごせた日を数えて生きていく「足し算命」というように生を考えるようになったのです。
今日、明日、明後日と過ごすにつれて1日1日と積み重ねて足し算していく方が、嬉しい生き方になり毎朝、「今日も生きている」と思って目覚めることが出来るのだといいます。
「死ぬ」ことは決して、楽しいことではないから、その余命が日々、減っていくのを憂うより、1日1日「今を生きる」ことを大事にしていくことの方が前向きになれるとてもいい考え方だと思いました。
緩和ケア医として
大橋先生は、現在(執筆当時)は、新たな抗がん剤を服用して腫瘍の増殖を抑えながら現役のホスピス緩和ケア医として働いています。
医者としてがん患者として患者と接することで、その体験を生かして患者と同じ目線で診療に当たっておられると思います。
末期のがん患者にとっては、こういう医者こそが、患者の痛みの分かる最も必要とされる医者であって、患者に寄り添うことが出来るのだと思います。
大橋先生にとっても自身の体験が役に立ち、患者からも必要とされて生きているという実感を得ているのではないかと思います。
そして、この本で、私が教えられたことは
人の死は、必ずやってくる。
人間の生は有限ということを念頭に置いて日々生きることが大切だ。
日常では、身近な幸せに気づきににくいけど生きることへの感謝を忘れないことです。
本書は、重くなりがちな厳しい闘病の様子や思いなど率直に綴られていますが、気さくなお人柄なのかときにはユーモラスな筆致でとても読みやすく決して、暗い印象になりません。
合間には、家族愛や人間愛が感じられる本なので医療関係者やがん患者のみならず、是非、色々な人に読んで欲しいと思います。
しぼり菜リズム

長年、医者として緩和ケアに携わっていた大橋先生が、がんになって初めて患者の真実が実感出来、実際には医師として接するがんと、患者として経験するがんは、全く別のものだと実感。
「自由に、患者風吹かせてしぶとく生きる」
「足し算式の人生」
「あきらめる、そして頑張る」
というように実体験から得た大橋流の生きることを諦めない前向きの姿勢などユーモア溢れる筆致で書いています。
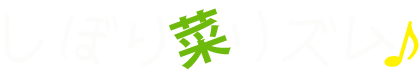

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15a8b7ba.957f61e3.15a8b7bb.83af7322/?me_id=1213310&item_id=19676362&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4823%2F9784575314823.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)















