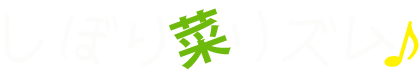『クリムト展 ウィーンと日本 1900』東京都美術館に行ってきました。
[ad#co-1]鑑賞方法の作戦
今回のクリムト展、クリムト(1862-1918)のウィーン、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館の所蔵作品を中心に日本では、過去最大級の油彩絵が展示されます。
中には、豊田市美術館、愛知県美術館など日本の美術館が所蔵している作品もあります。
巨匠クリムトの大規模な展覧会で、メディアでも連日、宣伝しているため東京会場は、終盤に近いこともあり平日の午後にも関わらず混んでいました。(チケット購入に10分程度並びます。)
展覧会は、クリムトやその家族に関係する展示、初期の自然主義的な作品から、金箔を多用した「黄金時代」の作品、日本美術の影響、官能的な女性、風景画、晩年の作品などクリムト作品の変遷を辿ることの出来る内容です。
今回は、沢山の展示があるので一つ一つ一つの作品や説明版を吟味していると最後の方は、疲れてしまい余裕を持って鑑賞出来なくなる可能性があります。
名画を鑑賞するのには、集中力とエネルギーが必要です。
なので、自分にとってもメインディッシュとなる見たい作品に時間を掛けたいので、興味のない脇役は端折って、順路通りに義理堅く見ないことにしました。
そのために、見るべき作品を絞って、目星をつけておきました。
事前にテレビ(NHKの『日曜美術館 エロスと死の香り~近代ウィーンの芸術 光と影~』)やネットでコレクションやクリムトに関する予備知識をある程度押さえておきました。
また、気になる作品を、戻って再び見るなど自分のペースで見れたので、一緒に行った知人とは館内では別行動だったのは正解でした。
私のメインディッシュ
私が楽しみにしていたのは、やはり分離派結成後の黄金様式の時代の作品です。
でもこの時期の作品は、クリムトの代表作が多く人気もあるため作品の前には二重、三重の人垣で、どうしても人の頭越しに見ることになります。
名画を限りなく近くで見たいので、頑張って横に回り込んだりしてして見ました。本当ならば、正面からじっくりと目に前で見たかったです。
それでも、「モナリザ」や上野の「パンダ」を見るように陳列物の前に立ち止まれないほどではないのがせめてもの救いでした。
エロいのだけどエロくない

出典:公式クリムト展 ウィーンと日本 1900 ユディト I
黄金様式の時代の絵の中で、私が一番、見たかったのは展覧会の目玉の『ユディト I』です。
ユディトは、聖書に出てくる勇敢で強い女性ですが、クリムトが描くユディトは、薄く開いた口元と挑発的な視線の官能的なものです。衣服から透ける裸体も艶めかしいです。
右脇の男性の頭は、敵将ホロフェルネスの生首です。
ユディトをネットで調べても確かに美しいけどここまで、官能的に表現したものはありませんでした。
神聖で英雄的なユディトをこのように誇張して「妖艶」に描いたことは、当時は、画期的なことだったそうです。
いかに「既存の芸術」を壊して自由に表現するというクリムトの意図が込められた作品になります。
実物の絵のタッチが細かいということでしたが、一番人気の作品故、黒山の人だかりです。可能な限り、(絵の横に回り込んで)近寄って見ると、顔などもが思った以上に多彩な色遣いで描かれていました。
クリムトの作品はこのような「性」を感じさせる官能的な女性は一つの魅力ですが、女性目線としてみても決して不快な感じはしません。
「ユディト I」にも言えますが、人物の肉体や表情は写実的で生々しいのですが、それを適度に抑えているのが背景です。
金箔をたくさん使った華やかな画面や複雑な模様の美しい背景の装飾は、まるで「宝石」のようです。それが、おとぎの国のようで現実感をなくしているからだと思いました。
露骨に男女の愛や性を連想させる官能的な表現さえもこの平面的で色彩豊かな背景によって、全体的にファンタジーのようになり、大衆の面前でも安心して見ることが出来る作品になったのではないかと思います。
「ユディト I」のように写実的(人物)なものと抽象的なもの(背景)交じり合って混沌とした不思議な感じが、人々を魅了するのではないかと思いました。
女性への愛

出典:公式クリムト展 ウィーンと日本 1900
クリムトについて一番驚いたのが、非常に女好きだったということです。
クリムトには、いろいろな女性との間に少なくとも14人の子どもがいたといいます。でも、生涯独身で、その誰とも結婚はしていませんが、本命の女性がいて生涯愛を貫いています。
アトリエには、半裸状態のモデルさんがいつもたむろしていて、複数のモデルさんと深い関係を持っていたこともあったようです。
クリムトは写真を見る限り、決してイケメンではありません。
でも、モテたのですね。クリムトと関わったどの女性からも文句が出ていなかったということで、誰からも憎まれなかったのは、常に女性に対してのリスペクトが大きかったのだと思います。
クリムトが単なる「エロおやじ」に終わらなかったのは、本分の「女性」をより魅力的に描く画家としての才能があったからでしょう。自分を美しく表現してもらえば、誰でも嬉しいものですよね。
今回の人物を描いた作品は、ほぼ女性です。
クリムトが自ら言うように「自分には関心がないが、女性に関心がある」とまあ、女好きというか本当に女性を愛おしんでいたのでしょう。
その他
黄金様式の作品の他に印象に残った作品があります。
額縁も芸術作品
クリムトの作品で面白かったのが、絵画を入れる「額縁」にも意匠が凝らしてあったことです。
特に金工師として活動していたクリムトの弟のゲオルグによる額縁の装飾が、クリムトの主要作品を引き立てていました。
また、『17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像』の額縁も、クリムトよって梅の枝や草花が描かれています。それが、日本風のモチーフで、クリムトが日本美術からの影響が伺われます。
日本の影響
展覧会タイトルにもなっている「ウィーンと日本 1900」の章では、クリムト作品に影響を与えた「日本美術」に触れています。
クリムトに影響を与えたのは、ヨーロッパ美術だけではありません。日本美術に関心があり、クリムトの絵にも影響を与えています。
実際に浮世絵や甲冑などの日本の美術品も多数コレクションしています。
額に日本風の絵を入れたり、クリムトの特徴である、金色を多用した色彩は、緒方琳派に影響を受けたといわれています。
『女ともだちI(姉妹たち)』の縦長の画面に2人の女性の立ち姿は、江戸時代の浮世絵の美人画に着想を得ているようです。画面左下に配された市松模様も日本の影響を受けています。
西洋文化とは違う日本独自のクールな表現が、新鮮で刺激になったと思われます。日本のものが取り入れられている作品には、よりシンパシーを感じてしまいました。
現実逃避
クリムトが亡くなって100年経っているので、心のうちは分かりませんがクリムトの作品には「現実逃避」が垣間見えるものもあるようです。
風景画

出典:公式クリムト展 ウィーンと日本 1900 丘の見える庭の風景
クリムトは実は内向的で女性のモデルを描くために女性といつも接していてこれが、気疲れになっていたというのです。
そのためバカンスで、大都市ウイーンを離れて、自然の中で風景だけを描いてストレスを発散させていたというのです。
そういう風にみると、クリムトの「風景画」は、伸び伸びと描いているような気がします。点描タッチの花々の抑えたような色彩は、静謐だけど実に豊かです。
クリムトの風景画にふと足を止めてしまうのも、優しく静かに時が流れるような作品に癒されて私自身もホッとするからです。
それは、現実から逃れたクリムトの「穏やかな心」が投影されているからというのもあるかもしれません。
死の予感

出典:公式クリムト展 ウィーンと日本 1900 家族
クリムトの晩年は、死をテーマに取り上げた作品が多くあります。
例えば『家族』という作品は、母と子どもの顔が白く浮かび、背景はほぼ黒一色です。
この黒が、「死」を連想させます。華やかな色使いの背景に黒を用いたものも多くあり、生の中の死を追求しています。
クリムトは父と右腕である弟の死、子どもの死といった肉親の死を経験し、自分の老いや死を感じていたところがあります。
女性を多く描き、多くの女性と関係を持ったクリムトは、よほど女性が好きなのかと思いました。
しかし、ネットで調べてみると実は、それだけの理由で女性ばかり描いているのではないという専門家の記事に目が止まりました。
クリムトが描く、官能的で輝くような女性の裸体は、生きることの美しさを象徴しています。
「性」を連想させるものは、「生きていること」の証です。頻繁に描かれた妊婦も旺盛な「生」を表現しています。
これら沢山描いた「生」の象徴は、死の恐怖からの逃がれるためのものではないかと解釈しているのです。
そういう見方をすれば、「死」の悲しみや恐怖から逃れるためにクリムトは、女性に傾倒していったのも分かるような気がしました。
しぼり菜リズム
クリムトは、ほぼ自分の作品一本で展覧会を黒字に出来る(武道館でコンサートが出来るミュージシャンのような)「ドル箱スター」なのが、今回よく分かりました。
日本では、本当に(特に女性に)人気ありますから。
改めて、クリムトの写実的なものと美しい色彩の紋様が織りなす装飾の融合に魅了されました。やはり、特徴的なクリムトの絵は、視覚を満足させてくれます。
同じ作家の絵を一堂に会した天覧会は、どうしてこの絵を描いたのか、何を伝えたかったのか。その作家の世界観やテーマが浮き彫りになるようで人物像に肉迫出来ます。
クリムトの作品は、どれもお洒落でモダンですが、作品に込められた思いは想像以上に深く重いものだと思いました。
■『クリムト展 ウィーンと日本 1900』公式サイト→